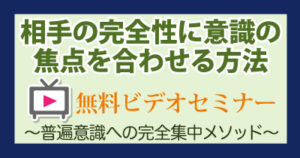《第17話》
この能力開発教材を販売する会社に入社が決まった時、採用決定の電話を受け取ったのは、スキーレジャーに出発する直前だった。
つまり、季節は冬。
あれから、季節は巡り、厳しい営業の世界で耐え抜き、再び冬がやって来た。
その知らせは、12月のある日。
当時、私のような成績の良くない社員は、月末になると先輩が上げた契約の書類を、出張して回収に回る。
先輩は営業活動を止めたくないが、月内業績になるため、正式な契約を取り交わすために足を運ばなくてはならない。
その使い走りの役回りを、私のような者にやらせるのだ。
実はこれが結構楽しみだった。
新幹線や飛行機に乗って、地方に出張させてもらえる。
営業活動のプレッシャーはないので気楽なものだったし、先輩には喜ばれ、自分も気分転換にもなる。
しかも、時には業績を自分にも分けてもらえた。
その日も、いつものように契約書回収の出張から戻り、オフィスに出社して自分の席に着いた。
しかし、みんなの自分を見る目が変なのだ。
「何かあったんだろうか?」とキョトンとしている自分を、ある先輩が「お前、知らされてないんか??」といって、掲示板のところへ連れて行ってくれた。
そこには異動の告知が貼られていた。
掲げられた告知書には、私一人の名前だけがポツリと書かれていた。
ここで、この先の話を理解していただくために、私がこの時、勤めていた会社の仕組みについて、少々触れておかなければならない。
この仕組みが分からないと、私の異動にあった背景と、この会社で私が所属した数年間の経験が、その後の私の人生に一体どんな意味をもたらしたのか理解できないからだ。
前にも説明したが、その会社の営業部は当時、大きく2つの部門に分かれていた。
一つは、私が最初に所属した、「電話営業」の部門。
そしてもう一つは「外交セールス」の部門だ。
電話営業部門と比較すると、正直、外交セールス部門は、私の異動当時、社内的にはかなり存在感が薄かった。
電話営業部門より、外交セールス部門で売上を伸ばすのは難しい(と思われていた)からで、事実、当時は会社の業績に大きく貢献していたのは、いつも電話営業の部門だった。
当時のこの会社の主たる営業スタイルは、まず、会社や商品へ問合せや反響があった方を見込み客として名簿を作り、そこへ電話営業部門の担当者が電話をかけ、商品を具体的にご案内する。
そこで興味を持っていただければ、契約となり、営業マンにもコミッションが入るシステムだ。
しかし、外交セールス部門は、会社が作った顧客名簿を与えられるのではなく、駅前でチラシを配ったり、ポスティングなどをして、自ら新規顧客開拓をしなければならない。
その分、成約すれば、営業マンに与えられるコミッションは電話営業の部署よりもずっと高いのだが、それはあくまでも「成約すれば」の話だ。
更に、外交セールス部門の役割としては、自ら商品を販売するだけでなく、私が入社前に商品のユーザーとして商品の販売を代行する代理店契約を結んだ様に、ユーザーの中から代理店を開拓し、育てていかなければならない。
余談だが、私が入社前の代理店時代に、「売り方が分からなければ、駅前でチラシを配ったらいい」と指導してくれた担当者は、この外交セールス部門にいた小野さんという人だった。
この外交セールス部門で課長を務めていた小野さんは、後に、私の良きライバルとして、しのぎを削ることになる。
話は戻るが、このようにして外部の人に代理店になって商品を扱ってもらうのだから、扱う商品は販売しやすい商品でなければならない。
だからこの部署では、その会社の数ある商品の中でも、ある主力商品だけを専門に扱っていた。
その主力商品は、一般的にも名前が良く知られた商品だったので、扱い易かったのだ。
しかし、その時に私が配属されることになった課は、外交セールスの部門の中でも、数年前に新設されたばかりの、主力商品とは別の商品を扱う課だった。
今後の話を展開させる上で、会社の主力商品を「A商品」、私が扱う事になったもう一つの商品を「B商品」としよう。
どちらの商品も、販売金額はほぼ同額。
一方は世間に名の知れた商品。
もう一方は、ほとんど知られていない商品。
どちらが売り易いかは、火を見るより明らかだった。
私が異動になった時、その「B商品」を専門に扱う課は、私の新しい上司となった今井次長と、私を入れてたった3人。
しかも、もう一人は私が異動した直後に辞めてしまった。
社内においても、正直、その存在すらほとんど知られていないような部署だった。
当時は、役職者として異動になる人以外には、部署をまたいで異動になることは異例中の異例だった。
私がいた当時も、営業部では初の出来事だったと聞いているし、その後、私が在籍した数年間でも聞いた事はない。
つまり私は、両方の営業部を経験した、とても貴重な存在だった。
しかし、周囲の目は、大半が同情と憐れみに満ちていた。
「あんな部署に異動になる(飛ばされる)なんて、かわいそうに…」
実は、この異動劇には隠されたドラマがあった。
異動後、その事実を知る事になるのだが、その時は知る由もない。